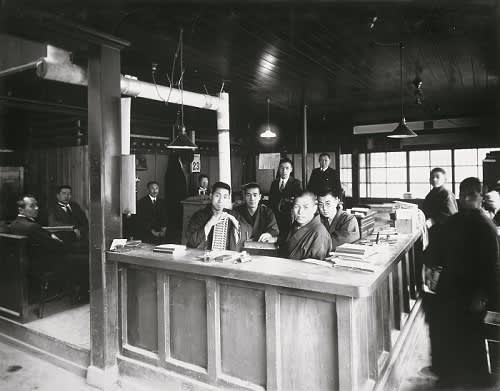動物と植物の循環から学ぶ持続可能な社会 | 武田薬品

動物と植物の循環から学ぶ持続可能な社会
2025年3月26日
私たちは地元の動物園と協力し、動物のフンや植物の根などを再利用して動物のエサを育てる循環型農業に取り組んでいます。3分の動画をご覧ください。
「我々の次の世代に、生き続けられる地球、この環境を手渡す必要があります」
京都市動物園の土佐祐輔さんは、持続可能な社会への思いをこう語ります。 京都の東に位置する京都市動物園には、ゾウやカバなどの哺乳類、アヒルやフクロウなどの鳥類、ワニや亀などの爬虫類など、多様な生物が暮らしています。100種600点以上の動物が暮らす京都市動物園では、エサの調達や糞(フン)の処理が課題になっていました。
京都市動物園とタケダは、こうした課題を教育の機会と捉え、「循環型農業モデル」を啓発する協働のプロジェクトを開始しました。動物園からはゾウやシマウマなど動物の糞(フン)を、タケダの京都薬用植物園からはゴミとして捨てられる予定だった植物の茎や根などを集め、たい肥の原料として使用しています。こうしてできたバイオマス由来のたい肥を使い、薬用植物や動物のエサとなるカボチャやピーナッツを、地域住民とともに育てています。
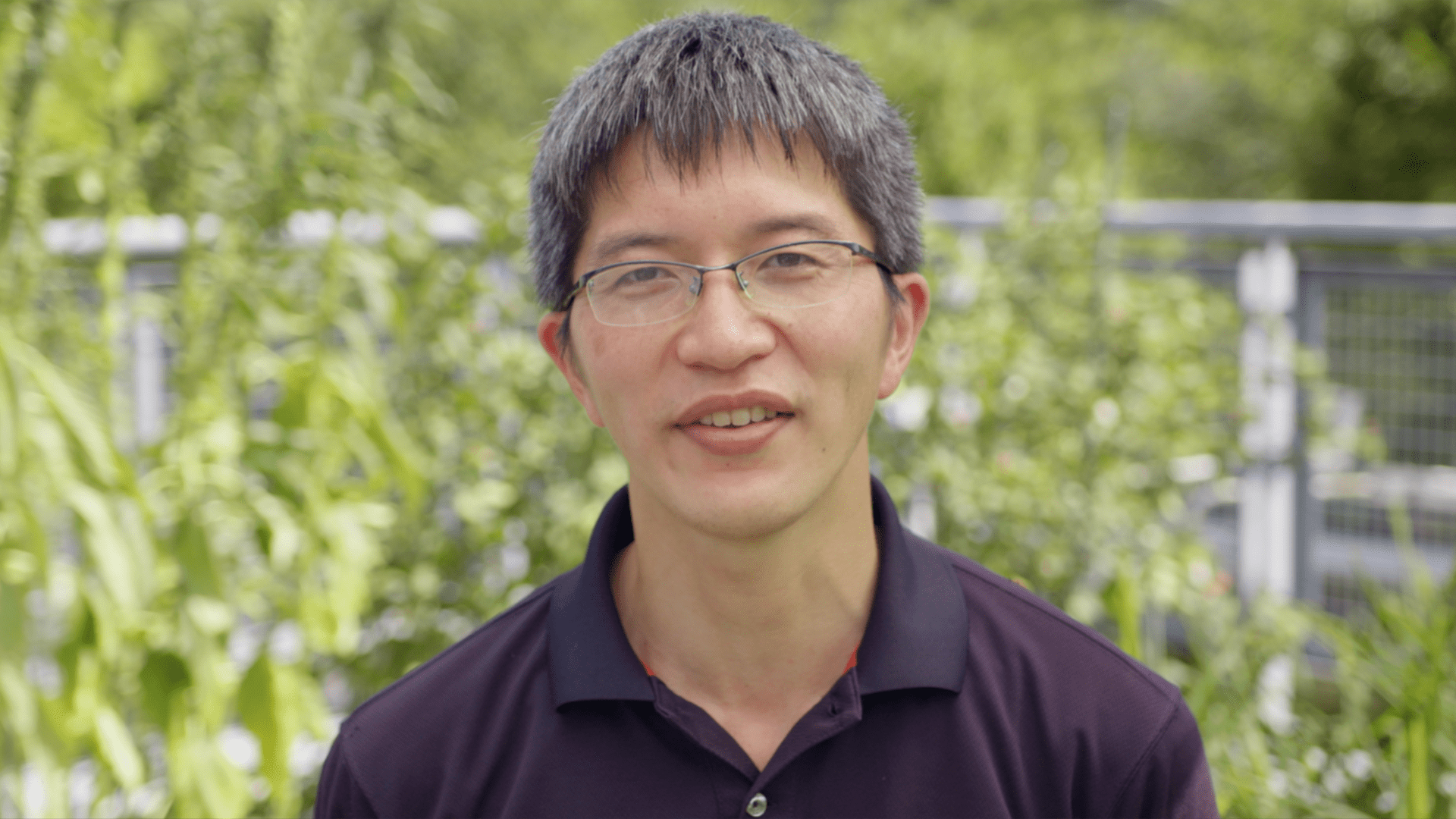
また、京都市動物園とタケダは、循環型農業モデルの相互展示や見学会などのイベントを開催しています。イベントを通じて、動物が循環型農業で育てた野菜を食べるところを、地元の小学生が見学しました。こうした取り組みについて京都市動物園の土佐さんは、「廃棄物を減らし、その再利用方法を考える―。将来の世代にそういった学びを提供していくことが私たちの使命です」と述べています。
タケダの京都薬用植物園でこのプロジェクトを担当する安藤匡哉は「動物がエサを食べるダイナミックな動きを見せることができました。子どもたちが驚く様子や楽しそうにしているのを見て、とてもやりがいを感じ、嬉しく思いました」と話します。
体験の場で学びを深める
タケダの京都薬用植物園は、京都市動物園だけでなく、さまざまな機関と協力し、植物の栽培技術承継や生物多様性の重要性を啓発しています。
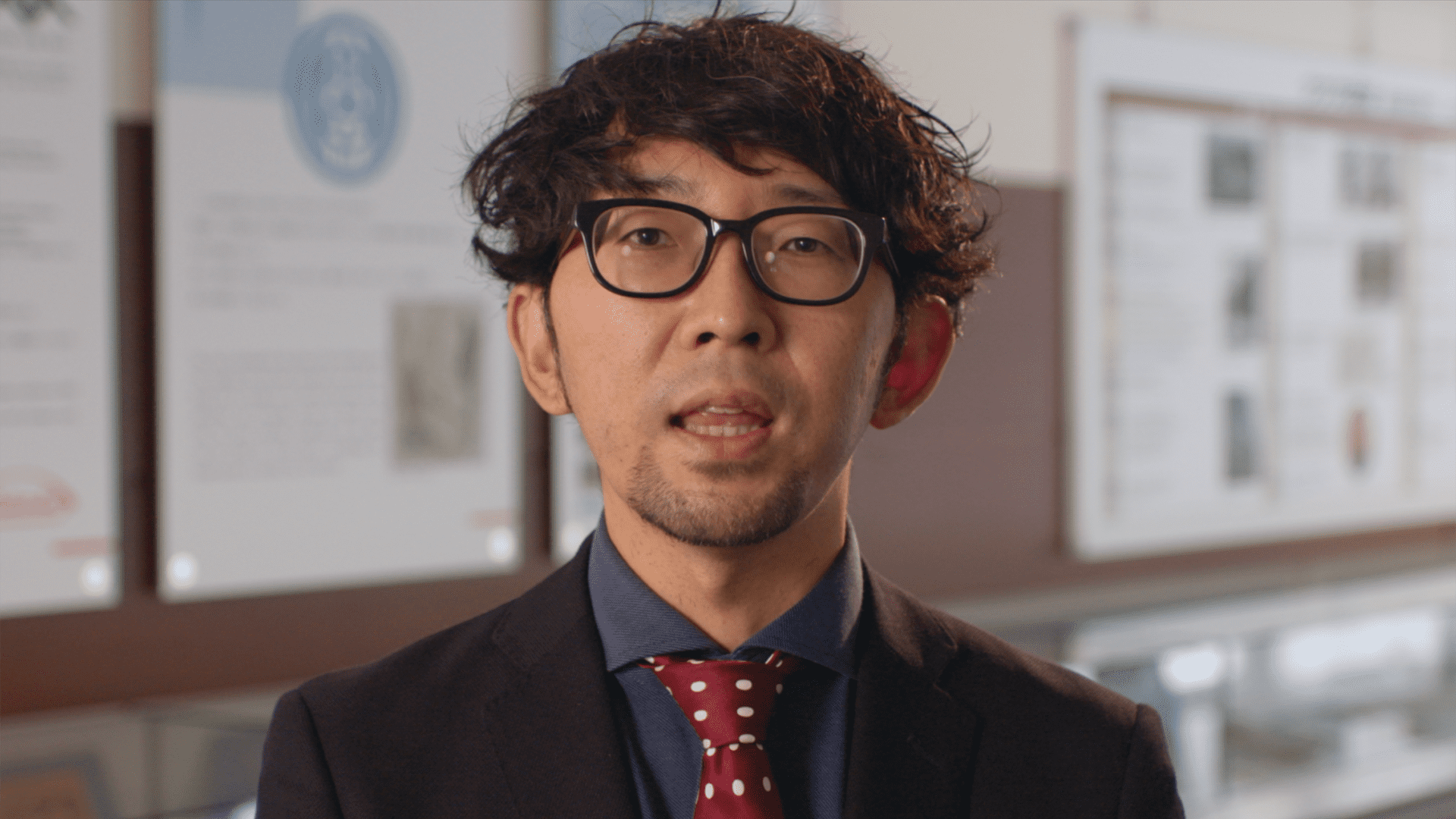
こうした取り組みが認められ、タケダの京都薬用植物園は「環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場」として京都市から認定を受けました。京都市環境政策局の山下僚太さんは、「環境保全への理解や、関心を深めるための取り組みとして、また、環境に対する気づきを得てもらう場として、(タケダの植物園は)非常に重要だと考えています」と話します。

タケダでこのプロジェクトを担当する安藤は「展示のみだと見るだけになってしまうので、植物に実際に触れてもらう機会を大切にしています。生物資源は、長い歴史の中で生態系により育まれてきました。人類の生活を支える生物資源が、生態系の破壊によって失われてしまうことがないように啓発が必要です。多くの人に知ってもらうことで、世界に尽くせるのだと感じています」と強調します。